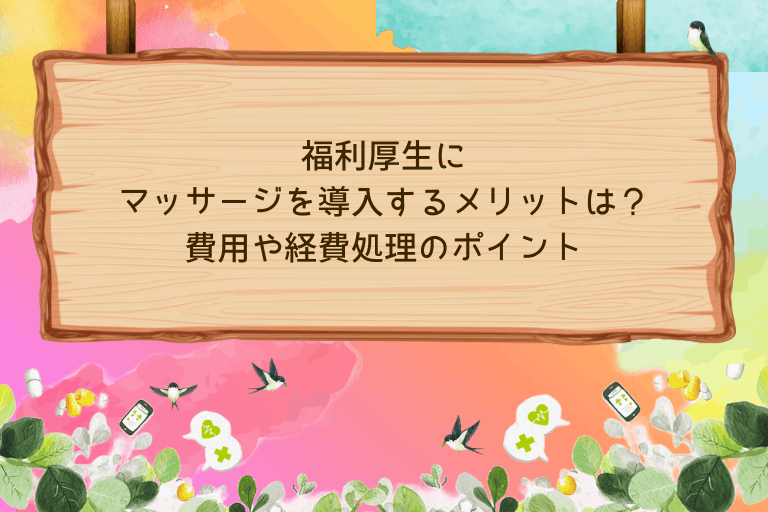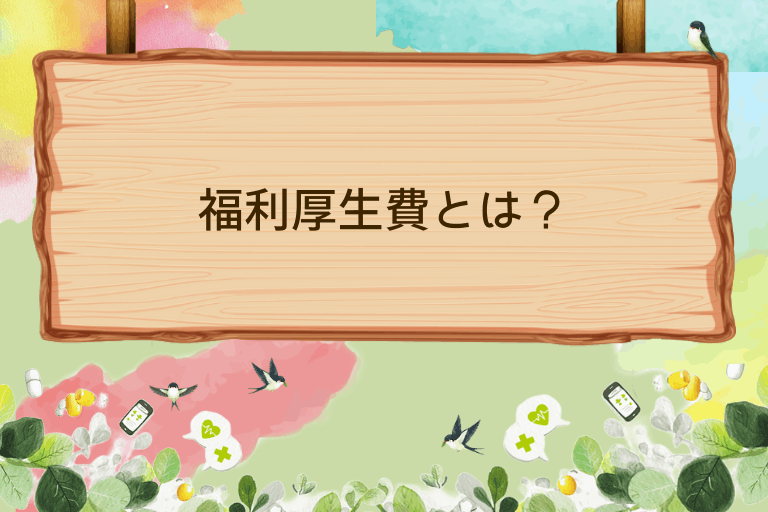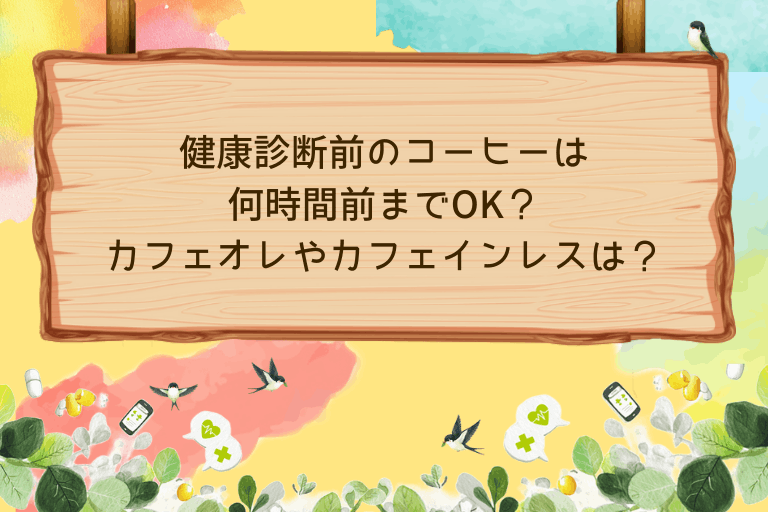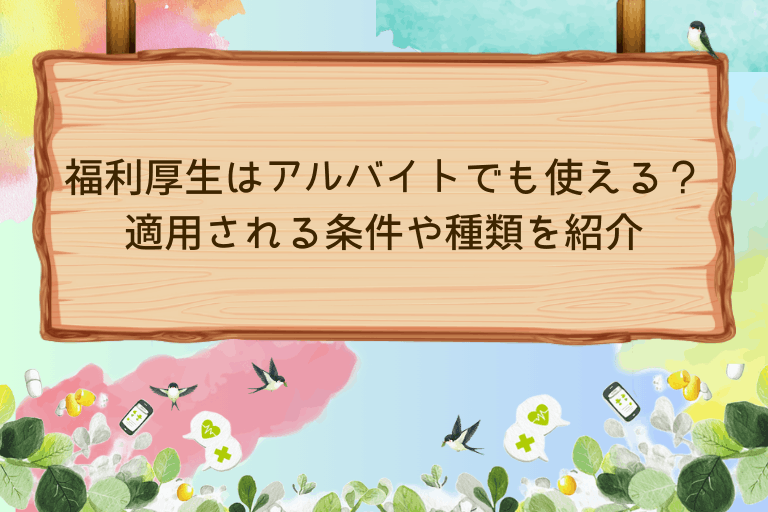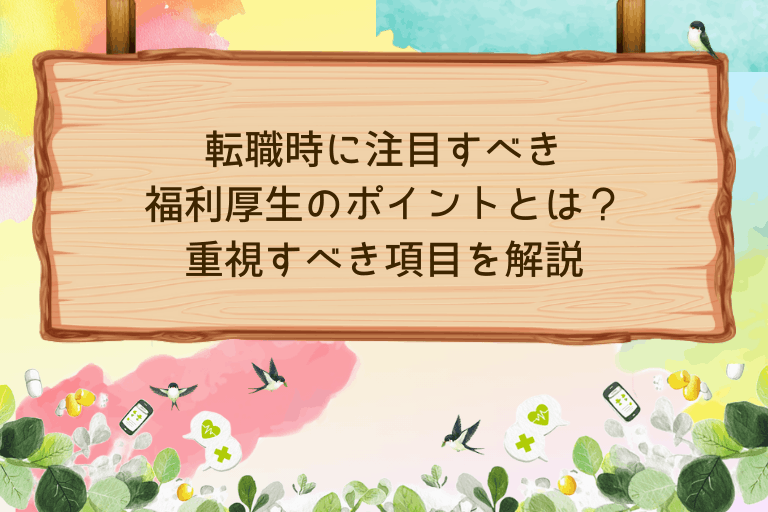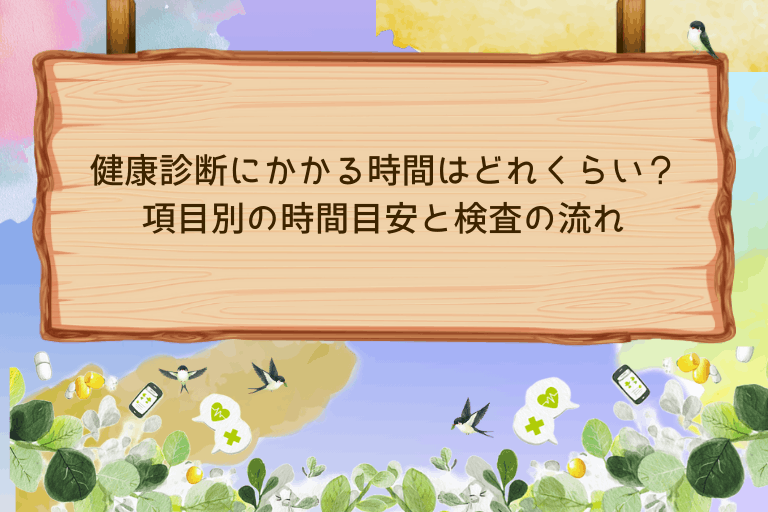役員の福利厚生はどこまで認められる?適用範囲と税務上の判断基準を解説
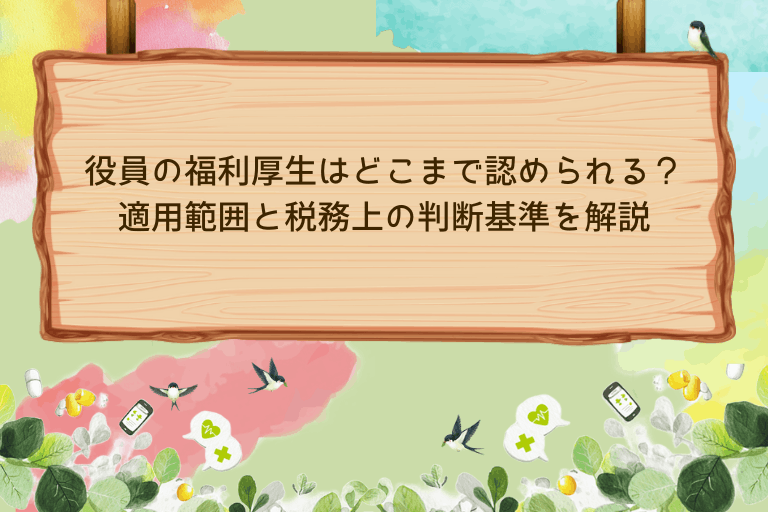
「役員には福利厚生を付けられない」「役員だけ特別扱いできる」──こうした誤解は非常に多く、実務では税務リスクにつながりがちです。実際には、役員も従業員と同様に福利厚生を利用できますが、運用を誤ると給与・報酬として課税される可能性があります。
本記事では、役員と従業員で福利厚生を共通に扱える原則から、慶弔見舞金や社宅など取り扱いが異なる例外、税務調査で否認されないための実務上の注意点までを整理します。「どこまでOKで、どこからNGか」を明確にしたい方は、ぜひ参考にしてください。
役員も従業員も同じ福利厚生を受けられる
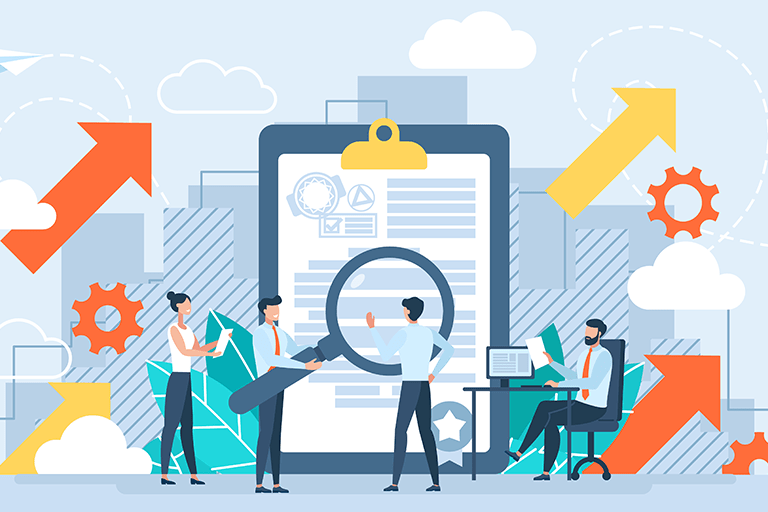
福利厚生は、役員と従業員で区別なく適用されるのが原則です。
法定福利厚生も法定外福利厚生も、役員だからといって除外されることはありません。
法定福利厚生には、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などがあります。
これらは法律で定められた制度であり、役員も要件を満たせば加入対象となります。
法定外福利厚生も同様に、社内で定めた制度であれば役員も従業員も平等に利用できます。
通勤手当や健康診断、社員食堂、慶弔見舞金などが該当します。
ただし、福利厚生費として計上するには、社会通念上妥当な範囲であることが求められます。
過度に高額だったり特定の役員だけが利用できる制度は、給与や賞与とみなされ課税対象となる可能性があります。
役員だけが使える福利厚生も存在しない
税務上、役員だけが利用できる福利厚生制度は認められません。
福利厚生費として非課税扱いにするには、全従業員が平等に利用できる制度であることが前提となります。
たとえば、役員専用の保養施設や役員だけに支給される特別な手当などは、福利厚生費として計上できません。
これらは役員報酬や給与として扱われ、所得税の源泉徴収が必要になります。
均等待遇の原則から、役員にだけ有利な制度を設けることは税務調査で指摘されるリスクが高まります。
福利厚生制度を設計する際は、役員と従業員の両方が同じ条件で利用できるよう規定を整備することが重要です。
役員と従業員で福利厚生の扱いが違うケース

原則として平等な福利厚生ですが、一部の項目では役員と従業員で税務上の取り扱いが異なります。
代表的なのが慶弔見舞金と社宅の2つです。
慶弔見舞金
慶弔見舞金は、結婚や出産、傷病、死亡などの際に支給される金銭です。
従業員に対する慶弔見舞金は、社会通念上妥当な金額であれば福利厚生費として非課税で処理できます。
一方、役員に対する慶弔見舞金は、金額によっては給与として課税対象になる可能性があります。
特に高額な見舞金は、役員報酬の一部とみなされるケースがあります。
税務調査で指摘されないためには、以下の点に注意が必要です。
- 社内規定で支給基準と金額を明確に定める
- 役員と従業員で著しく金額差をつけない
- 社会通念上妥当な範囲に収める
- 支給実績を記録として残す
慶弔見舞金の妥当な金額は、会社の規模や業種によって異なります。
同業他社の事例や過去の判例を参考に、常識的な範囲で設定することが求められます。
社宅
社宅制度も、役員と従業員で取り扱いが大きく異なる項目です。
従業員に社宅を提供する場合、賃貸料相当額の50%以上を本人から徴収していれば、差額は福利厚生費として処理できます。
しかし役員の場合、賃貸料相当額の計算方法が従業員よりも厳しく定められています。
役員に対しては、次の計算式で算出した金額以上を徴収しなければ、差額が給与として課税されます。
| 住宅の区分 | 賃貸料相当額の計算方法 |
|---|---|
| 小規模住宅(床面積132㎡以下) | (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
| 小規模住宅以外 | 市場価格の50%以上、または自社所有の場合は固定資産税の課税標準額をもとに計算した金額 |
役員の社宅については、会社が全額負担することは認められません。
必ず上記の計算式に基づいた賃貸料相当額を役員本人から徴収する必要があります。
また、豪華社宅(床面積が240㎡を超える場合など)に該当すると、時価が賃貸料相当額とみなされます。
社宅制度を導入する際は、税理士などの専門家に相談して適切な金額設定を行うことが重要です。
税務リスクを回避するためにすべきこと

役員の福利厚生で税務調査のリスクを避けるには、3つのポイントを押さえる必要があります。
社内規定の整備、常識的な範囲での運用、現金支給の回避です。
社内ルール・規定を明文化する
福利厚生制度は、必ず社内規定として文書化しておく必要があります。
口頭での取り決めや慣習だけでは、税務調査で福利厚生費として認められない可能性があります。
社内規定には、以下の項目を明記することが重要です。
- 制度の対象者(役員・従業員の区分)
- 利用条件や支給基準
- 金額の上限
- 申請方法と承認フロー
- 実施期間
規定を作成したら、就業規則や福利厚生規程として正式に制定し、全社員に周知します。
制度を変更する際も、必ず規定を改定して記録を残すことが重要です。
家族経営や個人事業主から法人化したばかりの会社では、規定の整備が後回しになりがちです。
しかし税務調査では規定の有無が重視されるため、早い段階で整備しておくことをおすすめします。
福利厚生費は常識的な範囲で抑える
福利厚生費として認められるには、社会通念上妥当な範囲であることが前提です。
過度に高額な支出や、一般的な水準を大きく超える内容は、給与や賞与とみなされます。
たとえば健康診断の費用は、一般的な検査項目であれば福利厚生費として計上できます。
しかし人間ドックや高額なオプション検査を役員だけに実施する場合は、給与として課税される可能性があります。
通勤手当についても、実際の通勤にかかる費用の範囲内であれば非課税です。
しかし非課税限度額を超える部分や、実際の通勤経路と異なる金額を支給すると、所得税の課税対象となります。
福利厚生制度を設計する際は、同業他社の事例や業界水準を参考にすることが有効です。
節税を意識しすぎて過度な支出をすると、かえって税務リスクが高まることを理解しておきましょう。
現金支給はNG
福利厚生は、原則として現物支給やサービス提供の形で行う必要があります。
現金で支給すると、福利厚生費ではなく給与として扱われ、所得税の課税対象になります。
たとえば、社員食堂で食事を提供したり食券を配布する場合は福利厚生費として認められます。
しかし「食事代」として現金を支給すると、給与とみなされて源泉徴収が必要になります。
住宅手当も同様に、現金で支給すると給与として課税されます。
福利厚生として扱いたい場合は、社宅制度として現物提供する形にする必要があります。
役員兼従業員の立場の人がいる場合も、現金支給は避けるべきです。
福利厚生の趣旨を明確にし、現物またはサービスの形で提供することで、税務上の問題を回避できます。
まとめ
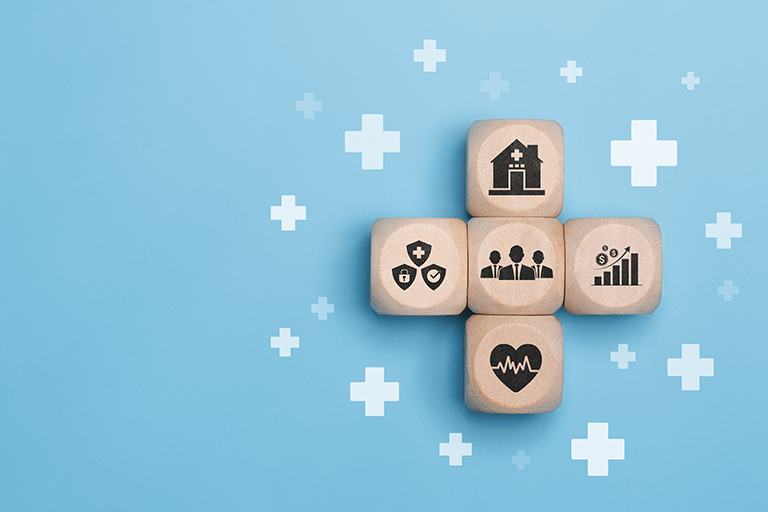
役員も従業員と同じ福利厚生を受けられますが、税務上の取り扱いには注意が必要です。
原則として平等な制度設計が求められ、役員だけが利用できる福利厚生は認められません。
ただし慶弔見舞金や社宅については、役員と従業員で計算方法や基準が異なります。
特に社宅の賃貸料相当額は、役員の場合より厳格な計算式が適用されるため、専門家への相談が推奨されます。
税務リスクを回避するには、社内規定の明文化、常識的な範囲での運用、現金支給の回避が重要です。
これらのポイントを押さえることで、適切な福利厚生制度を構築し、税務調査でも問題なく説明できる体制を整えられます。
福利厚生は従業員満足度を高め、優秀な人材を確保するための重要な施策です。
法人税や所得税の仕組みを正しく理解し、適切に運用することで、会社にとっても役員・従業員にとってもメリットのある制度を実現できます。